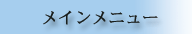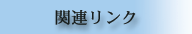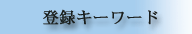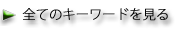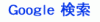 |
第4巻
 阿部 里加 Rika Abe
阿部 里加 Rika Abeアーレントの意志論における内的能力としての決意
Volition as an inner capacity in Arendt’s Willing
2012年12月 発行
[ 要旨 ]
アーレント最晩年の意志論は〈始まり〉の概念で周知されている。しかし、より注目すべきは決意 (volition)の概念に関する議論である。ラテン語で「決める力」「選択する意志」を意味する決意は、人間が世界の中でどのように現れたいかを決める内的能力である。ここでのポイントは、現れるための彼の決定や意欲が彼のものであるという点にある。
決意を理解するために、筆者は思考と意志の違いに注目する。思考は主として現れに関与し、自己には関与しない。現れのために、思考は観察者として世界を見ることによって自己を世界に折り合わせる。対して意志は、現れに関与せず、世界から退きこもることによって内的自己に配慮する。こうした自己の配慮は、意志の内的分裂、すなわち命令―抵抗の構造としての内的分裂から生じる決意に起因しており、決意は内的人間に意志の命令に抵抗させる。決意は逆説的で自己矛盾した能力であるが、歴史的には我々の生活の特殊な領域である人間の内面性を発見した点で重大な帰結をもたらすとアーレントは述べる。
暗闇にある内的能力についての彼女の議論はこれまでアーレント思想の否定的な側面として批判されてきたが、今や内的能力が歴史や倫理において果す重要な役割に我々は気づくべきである。彼女は内的能力を最後の著作のみならず中期の著作である『人間の条件』や『革命について』、『イェルサレムのアイヒマン』においても考察している。アイヒマンのいくつかの言動は、彼が歴史から離れて彼の過去の行為を反省することで、終には彼自身を発見したという事実を示している。この事実は、意志論にしたがえば、決意が、彼の行為のみならず性格にたいしても責任を担いうる人格を創造した過程であると理解可能である。
[ Abstract ]
Willing, Hannah Arendt’s last work, is known for the concept of “beginning”; however, a remarkable argument has arisen over its notion of “volition.” “Volition,” which means “the power to decide” or “the will to choose” in Latin, refers to man’s capacity to decide on the form of his worldly presence. His choice of and wish for a certain appearance are his own.
With regard to the differences between thinking and willing, the former deals mainly with appearance and not with the self. Thinking permits the self to come to terms with the world by watching it as a spectator. In contrast, willing, by withdrawing from the world, is not concerned with appearance but only the inner self. This caring for the self is caused by the internal, command-resistance division of the will; it is precisely “volition” that permits inner man to resist the orders of the will. While Arendt sees “volition” as a paradoxical, self-contradictory faculty, it provides the foundation for human inwardness as a special region of existence.
Although Arendt’s arguments about the inner capacity have been criticized as a negative aspect of her thought, we should notice the imperative role of this capacity in history and ethics. Arendt explored the inner capacity not only in her last work but also in her middle writings, such as The Human condition, On Revolution, and Eichmann in Jerusalem. Some of Eichmann’s behaviors and words show us that he reflected on his past acts by turning away from history and eventually discovering himself. According to Willing, we can understand this fact as a process in which “volition” creates the person who can be held responsible both for his action and his character.